子育てや住宅購入、将来の備えを考えるとき、避けて通れないのが「社会保険」。
言葉はよく聞くけど、実はよく知らない…そんな方も多いのではないでしょうか?
今回は、社会保険の基本と、働き方・家計にどう関わってくるのかを、わが家の考えも交えてご紹介します。
社会保険ってなに?
社会保険とは、生活上のさまざまなリスクに備えるための「公的な保険制度」のこと。主に次の5つで構成されています。
- 医療保険:病気やけがをしたときの医療費の負担を軽減
- 介護保険:40歳以上が対象。将来の介護に備える
- 年金保険:老後の生活や、遺族・障害があったときの保障
- 雇用保険:失業したときや育児休業中の手当など
- 労災保険:仕事中のけがや通勤中の事故に対する保障
これらをまとめて「社会保険」と呼びます。会社員として働いている場合は、給与から自動的に天引きされています。
医療保険
| 区分 | 保険の種類 | 対象となる人 | 保険者(運営) | 保険料の支払い | 主な特徴 |
| 会社員 | 健康保険 | 企業などに勤めている人(正社員など) | 健康保険組合 or 協会けんぽ | 会社と折半 | 扶養家族の分は追加負担なし |
| 公務員など | 共済組合 | 国家・地方公務員、教職員など | 各共済組合 | 給与天引き(折半) | 給付がやや手厚いケースあり |
| 自営業・無職 | 国民健康保険 | 自営業、フリーランス、退職者など | 市区町村 | 世帯ごとに計算 | 扶養の概念がなく、1人ずつ保険料がかかる |
| 75歳以上の人 | 後期高齢者医療制度 | 75歳以上のすべての人 | 各都道府県の広域連合 | 原則:年金天引き | 1割〜3割の自己負担(所得に応じて) |
- 自己負担割合:原則として医療費の自己負担は【70歳未満:3割】【70〜74歳:2割または3割】【75歳以上:1〜3割】
- 高額療養費制度:医療費が高額になったときは、一定の上限を超えた分が払い戻されます。
- 出産・育児・休業中の給付:会社員の場合、出産手当金や傷病手当金などの給付があり、自営業者にはない点に注意。

扶養内で働くかどうかも重要なポイント。
年収が130万円を超えると扶養から外れ、自分で社会保険に入る必要が出てきます。
ですが、将来の年金受給額や育休手当のことを考えると、扶養を外れて働くメリットもあります。
介護保険
介護保険制度は、2000年に始まった国の公的制度で、介護が必要になったときに介護サービスを受けられる仕組み。
40歳以上の人が保険料を支払い、要介護状態になったときにサービスが受けられるようになります。
働く世代は、将来自分も使うかもしれませんが、その前に自分の親が使う可能性が高いですね。
◇第1号被保険者(65歳以上)
・要介護・要支援と認定されれば、介護サービスが利用可能。
◇第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)
・老化に起因する16種類の病気(例:認知症、脳血管疾患など)が原因の場合に利用可能。
保険料は40歳以上であれば給与天引きなどで支払われており、知らないうちに備えていることが多いです。
介護が必要になったら、市区町村の窓口で「要介護認定」を申請します。
認定されると、要支援1〜2、要介護1〜5の区分に応じて、
訪問介護・デイサービス・施設入所などが利用可能になります。
利用者は原則1割〜3割負担でサービスを受けられます(所得に応じて異なる)。
年金保険
| 項目 | 内容 | ポイント |
| 公的年金の種類 | 国民年金(基礎年金)と厚生年金の2階建て | 正社員・パートなど働き方によって加入先が変わる |
| 加入対象 | 20歳以上60歳未満のすべての人が対象 | 専業主婦・育休中も一定条件で加入対象 |
| 第1号被保険者 | 自営業・フリーランス・学生など(国民年金のみ) | 働き方を変えた場合に該当することも |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員(厚生年金+国民年金) | 産休・育休中も「みなし賃金」で厚生年金加入が継続 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者の配偶者(年収130万円未満、扶養内) | 扶養に入っていれば自分で保険料を納める必要なし |
| 保険料の支払い | 第1号:自分で納付 第2号:給与天引き 第3号:保険料なし(国負担) | 働き方が変わると支払方法も変化 |
| 将来もらえる年金 | 老齢年金・障害年金・遺族年金の3つ | どの働き方でも、加入年数と保険料に応じて将来受け取れる |
| 育休中の取り扱い | 保険料免除+将来の年金額に影響なし(第2号の場合) | 育休中も「年金が減らない」のはママにとって大きな安心材料 |
| パート勤務の注意点 | 月収8.8万円以上(年収106万円以上)などで厚生年金加入の対象になることがある | 扶養内で働くのか、厚生年金に加入するのかで将来の年金額が変わる |
- 働くママにとって「扶養内」「正社員」「フリーランス」などの働き方の選択が、公的年金の加入区分に直結します。
- 育休中の厚生年金免除制度は、知らないと損をすることもあるため要チェック。

将来の年金を意識した「働き方」「収入の設定」「扶養の出入り」は家族全体のライフプランに影響するので、慎重に考えました。
⇒年金については次の記事でもっと詳しく載せます
労災保険
労働者が「仕事中や通勤中にケガや病気をした場合」に補償を受けられる保険です。
会社(事業主)が全額負担しており、労働者は保険料を払っていません。
正式には「労働者災害補償保険」といい、仕事中や通勤中のケガ・病気・障害・死亡などを補償する公的保険です。
正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員など、すべての労働者が対象です。
雇用形態にかかわらず、「労働者」として雇われていれば、自動的に労災保険の対象になります。
■給付の種類
- 療養補償給付(治療費の支給)
- 休業補償給付(休業中の所得保障:給料の約8割)
- 障害補償給付(後遺障害が残ったとき)
- 遺族補償給付(亡くなった場合に家族へ)
例えば
・業務中のケガ・病気
例)職場で転倒して骨折した、重い荷物で腰を痛めた
・通勤中の事故・けが
例)通勤途中に交通事故にあった、自転車で転倒した(子どもを保育園に送った後の通勤中など)
・仕事が原因の病気
例)パソコン作業による腱鞘炎、過労によるうつ病 など
・仕事中の死亡事故や後遺障害
遺族への給付や障害補償も含まれます
雇用保険
雇用保険は、働いている人が「失業したとき」や「育児・介護のために休業するとき」など、仕事を続けられない期間に一定の給付を受けられる公的制度です。
会社に勤めている人の多くが、自動的に加入していて、給与から保険料が天引きされています。
| 種類 | 対象者 | 内容・目的 | 支給例 |
|---|---|---|---|
| 基本手当(失業手当) | 離職した人(求職中) | 再就職までの生活を支える手当 | 退職後にハローワークで申請すると、一定期間支給される |
| 育児休業給付金 | 育児休業を取得する被保険者 | 育児休業中の所得を一部保障 | 原則子どもが1歳になるまで、賃金の67%→50%支給 |
| 介護休業給付金 | 家族の介護で休業する被保険者 | 介護休業中の所得を一部保障 | 最大93日間、賃金の67%支給 |
| 高年齢雇用継続給付金 | 60歳以上で働き続ける人 | 賃金が大幅に下がった人への補填 | 賃金の最大15%程度を支給(条件あり) |
| 教育訓練給付金 | 雇用保険に一定期間加入していた人 | 指定の講座・資格取得の費用を補助 | 受講費の20~70%を支給(講座により異なる) |
雇用保険は、以下の条件を満たすと加入対象になります
- 週20時間以上働いている
- 31日以上の雇用見込みがある
正社員はもちろん、パート・アルバイトでも条件を満たせば加入対象になります。
- 会社と労働者の両方が保険料を負担しています(給与から引かれています)。
- 現在働いていないと加入はできません(過去の加入実績があれば、育児給付などを受けられることも)
まとめ
社会保険料は、毎月の手取りに直結します。
でも、単なる「支出」ではなく、保障のある貯金のようなものと捉えることもできます。
例えば:
- 健康保険に加入していれば、医療費は原則3割負担で済む。
- 厚生年金に加入していれば、将来の年金が国民年金より多くなる。
- 雇用保険に加入していれば、育休手当や失業手当の対象になる。
短期的には手取りが減るように感じても、長期的に見るとリスクに備えられるという意味で、家計に安心をもたらす制度です。実際に自分が給付を受けてみないと実感が湧かないかもしれません。

私が産休育休に入る前、パートになるか、正社員を続けるかと悩みましたが、正社員を続けることにしました。
・育児休業給付金が受け取れる(雇用保険加入が条件)
・将来の年金に差が出る
・医療や介護の保障も安心…など
もちろん、保育園のことや家事育児とのバランスなど悩みは大きかったですが、「保障を得ながら働けるのは今だけかもしれない」という気持ちで決めました。
これからの暮らしのためにできること
社会保険は、一見わかりにくい制度ですが、家族の将来を守る大切な仕組みです。まずは「自分がどの制度に入っているのか」「何が受けられるのか」を知るところから始めましょう。
おすすめは、無料のFP相談を活用すること。リクルートさんなので安心です。
保険・家計・働き方をトータルで見てもらえるので、「何を選べばよいのか」がぐっとクリアになります。
\ 家計の不安を解消したい方へ /
👉 リクルートが運営する保険チャンネル
手取りが減っても、安心を得られる「未来への備え」になる
わが家は正社員として働き続け、保障と収入のバランスを重視家計と向き合う中で、社会保険を味方につけることは、未来を描く第一歩です◎
「知ってよかった」「もっと早く知りたかった」と思えるような制度、ぜひ一度見直してみてくださいね。

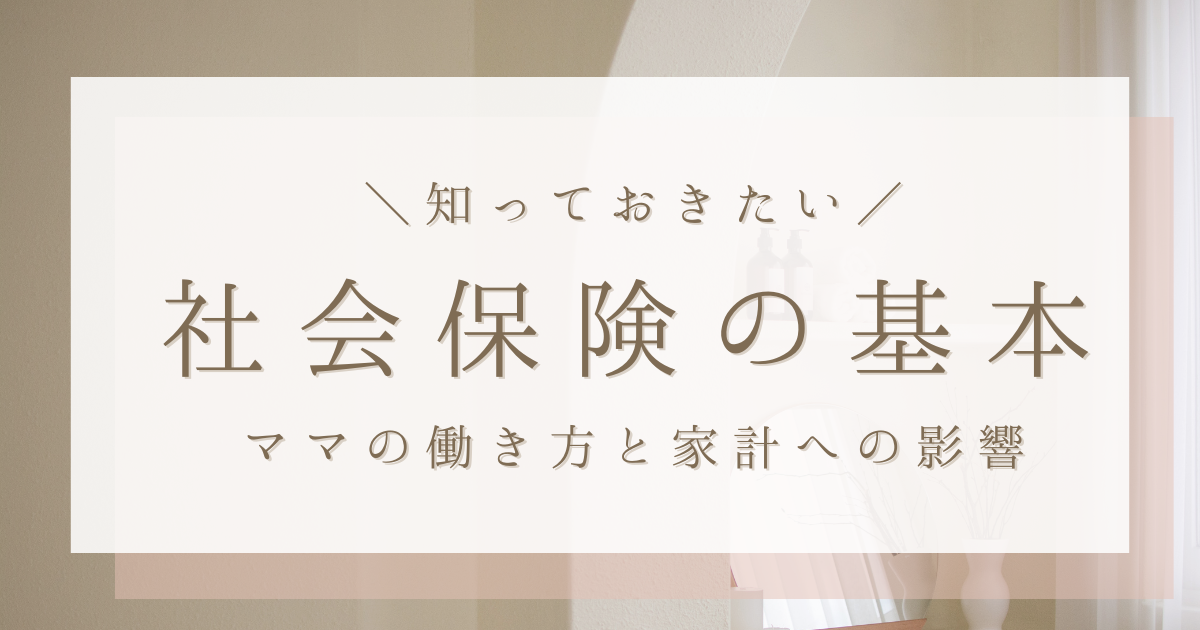

コメント